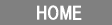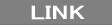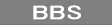|
||||||||||
なにわの春は野崎参りから〜
元春日神社、神武天皇の足跡、石切神社まで…
フルメンバーポタ
御供田〜平野屋(10)
久々のフルメンバーポタは
上方落語の3代目桂春団治氏の十八番
思い出しながら〜
えっ?浮ドン
野崎参りは東海林太郎氏??
歌かいな〜〜汗
※マウスポインターを置いてください。
撮影:平成26年05月03日
UP日:平成26年05月10日
 お腹も膨れたし〜 路地の先は〜 ピンぼけスミマセン。。 ※ 御供田八幡神社 この辺は前にも〜 本日十一社目 |
 境内地の榎 |
 手水舎 ※河内國讃良郡御供田村(古は團野村)石清水八幡宮の社領となりしより御供田村と地名を改む 團野浄忍入道 八幡宮を勧請して一村の氏神とす(元禄の初 平成14年起算約310年前) 男山八幡宮から勧請されたとか。 本日、通ってきた八幡宮は 同じく 勿入淵(ナイリソ) 清少納言の枕の草子、第17段に「淵は……、ないりその淵、……。」と出てきます。 「勿入」とは、強い禁止を表し、絶対に入ってはいけないという意味です。 危険だから入ってはいけないという意味なのか、たくさんの魚が捕れて、 部外者を入れようとしなかったのか、今ではよく分かりません。 古来、河内平野は大和川の流入する沼沢地で、江戸時代、 東の深野池とは別に、市域、諸福から東大阪市、長田辺りにまで広がる勿入の淵があったといいます。 所によっては、ナイスケの淵ともいい、内助の淵と書きました。 これはナイリソがナイジョに転訛(てんか)し、これに「内助」の字をあて、 更にナイスケと読むようになったと思われます。 宝永元(1704)年、大和川付替工事によって河内平野は急速に新田開発されました。 ※「勿入淵址」は諸福6丁目にあります。(広報だいとう:より) の名残でしょうか? |
 御供田の旧村名、團野の名が入っています。 (個人名のようですがね) ※ |
 拝殿社と本殿舎 改築されています。 ※明治期に建て替えられた 鳥居ですと〜 |
 ミーティング中 生駒まで行けるのか?と… ※神社脇の路地 |
 井戸も残されています。 ※個人宅の椋木 |
 緑が眩しい時期です。 ※ |
 東向いて〜 生駒へ ※南向いて〜 恩智川上流部 |
 恩智川下流部 此処で西に向きを変えて〜 ※泉町 |
 銭屋橋 新田開発の名残ですね。 前には〜 ※この河川の上流部に1級河川大川銘が〜 前に |
 平野屋会所(高松邸) 宝永久元年(1704)大和川の付け替え後 東本願寺難波別院の手で新田開発され、 工事完了後の正徳4年(1714)に平野屋又右衛門に譲られた。 その後所有者は助松屋、天王寺屋、高松長左衛門と移った。 会所とは年貢の徴収と管理に当たる所。 (今は取壊された、敷地には舟入場、千石蔵などが在った、 母屋は江戸初期と推定され 広い土間と大引き天井で居間と書院、 屋敷内には瓢箪型の池をもつ庭園も在った。) 会所の建物が現存するのは鴻池新田会所とここの二ヶ所だけだったのに無くなりました。 (深野南の歴史より)編集 庭園跡?前は〜 ※坐摩神社 本日十二社目 |
 手水舎 ※当新田開発に伴い享保13年(1728)に 平野屋の手によって 大阪総社から勧請されたものである。 生井(いくい)、福井(さくい)、綱長井(つながい)、波比岐(はひき)、阿須波(あすは)の 五つの神を総称して坐摩神(いかすりのかみ)といい 住まいの神、旅行安全の神、安産の神として広く信仰される。 手水舎の水盤は安永6年(1777)の献納明記が狛犬は弘化3年(1846)の明記がある |
 本殿舎 ※白壁土蔵〜 道路に分断されて 変な感じ… |
 新興住宅地と新しい道路で〜 前は薄暗い境内地でした。 ※ |
 抜け道にも成っています。 ※一本一得? |
 向こうに行けば着かないですよ! ※酒か醤油造り用の石材料 |
 街道は続きます。 竜間街道へ〜 ※立派な屋門も〜 |
 もっと大きな屋門も〜 ※外環状を渡ります。 |